災害史から防災を学ぶ・・・磯田道史著「天災から日本史を読みなおす」
いつやってくるかわからない災害も、歴史を調べると予測がついて備えることはできる。
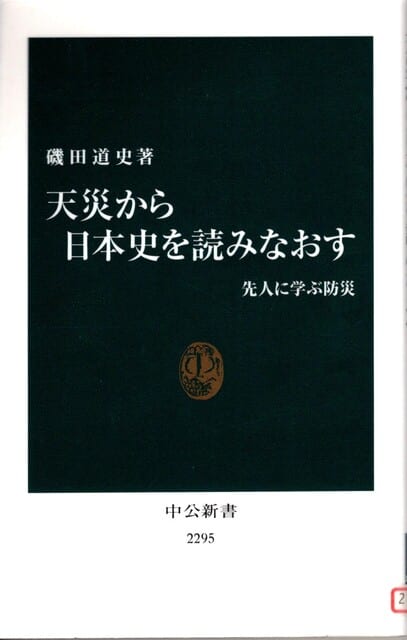
本書によると最後に富士山が噴火した「宝永の噴火」は、群発地震の5年後に発生。12日間も江戸市中の空を火山灰がおおい、昼でも提灯が必要なほど暗くなり、ガラス質の降灰が目の中にはいって往生した人が多かったらしい。

歴史上、富士山や浅間山が噴火すると冷害となり、飢饉が数年つづいたことも忘れてはならない。

能登豪雨の後も泥濘が乾いて粉塵となって舞い、喘息になった人もいたし、泥だし作業には防塵マスクとゴーグルが必需品だったと聞く。
とくに首都圏在住の人は、ゴーグルと使い切りタイプの目薬、防塵マスクを常備しておいたほうが無難だろう。

防塵マスクは普通のマスクで兼用せず、乾いた個体粉塵用の「DS1」規格以上の個体粉塵向けの業務用を推奨したい。数値が高いほど集塵率が高く、使い捨てタイプの市況価格は1枚200円前後だ。
投稿者プロフィール

-
ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。
縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。





